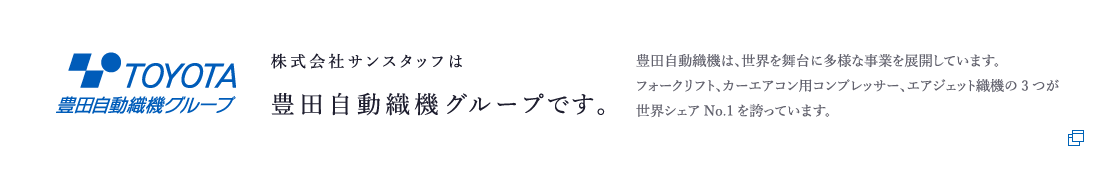一般派遣について
- Q「派遣」とは、どんな仕組みですか?
- A
 派遣は、派遣元であるサンスタッフと雇用契約を結んだ派遣スタッフが、派遣先企業の指揮命令のもと仕事をするサービスです。
派遣は、派遣元であるサンスタッフと雇用契約を結んだ派遣スタッフが、派遣先企業の指揮命令のもと仕事をするサービスです。
派遣スタッフの雇用主は、派遣元となります。
派遣元は派遣スタッフに対し、お給料の支払いや福利厚生、スキルアップ研修などを通じて、派遣社員をサポートします。
派遣先企業は派遣社員に対して仕事の指示を行います。
- Q派遣開始前に派遣スタッフの面接を行うことはできますか?
- A
労働者派遣法では、「派遣労働者を特定することを目的とする行為」を禁止しております。そのため派遣先による事前面接や、履歴書の提出を求めることはできません。(但し、紹介予定派遣を除きます)
解説:
法律上の解釈では、スタッフを派遣先に派遣する行為は労働者の配置であり、誰を派遣するかの決定は雇用関係のある派遣元事業主(サンスタッフ)がおこなうものとされています。
仮に派遣先が派遣スタッフの選考を行ったり、特定の派遣スタッフを指名し派遣元事業主がそれを拒否できないような場合、派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される可能性があり、その場合、労働者派遣法第26条「派遣労働者を特定することを目的とする行為」に抵触し、派遣元事業主及び派遣先とともに罰則の適用を受けることがあります。
誰をどこに派遣するかを決められるのは、唯一その雇用者である派遣元のみです。派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣社員を特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と派遣社員との間に雇用関係を認めるようなものであり、許されません(派遣法第26条7項、職業安定法第44条)。
- Q受け入れ期間にはどのような制限があるのでしょうか?
- A
事業所単位と個人単位(組織単位)といった2つの期間制限が設けられています(派遣法第40条の2、第40条の3)。
解説:
1.事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣労働者の受け入れ可能期間は、原則3年となります。
※派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行うことで、3年を超える受入れが可能です。2.個人単位(組織単位)の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣労働者の受け入れ可能期間は、3年となります。
Point. 上記期間制限について以下の例外対象が設けられています(派遣法第40条の2第1項)。
- 派遣元(サンスタッフ)での無期雇用派遣労働者
- 60歳以上の労働者
- 日数限定業務
- 有期プロジェクト業務
- 産休育休・介護休業代替業務
尚、紹介予定派遣では、最長6ヶ月と決められています。
- Q事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限はどちらが優先されますか?
- A
事業所単位の期間制限が優先されます。
解説:
つまり、事業所単位の期間制限が到来し、その後の延長がなされない場合、その時点で同一組織単位で1年しか受け入れていない派遣労働者については、事業所単位の期間制限を超えて受け入れることができません(派遣法第40条の2、第40条の3)。
- Q個人単位の派遣期間制限を迎える際、部署を変えて引き続き同一派遣社員を受け入れることは可能ですか?
- A
組織単位を変えれば、同一の事業所内に、引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)受け入れることは可能ですが、派遣先事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。
解説:
この場合でも、派遣先は同一の派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにする必要があります。
- Q派遣労働者に適用される就業規則は、派遣先・派遣元どちらのものですか?
- A
派遣元の就業規則になります。
解説:
雇用主であるサンスタッフの就業規則が適用されます。サンスタッフでは、派遣開始前にビジネスマナー研修を行っており、派遣先の就業規則やルールについても十分理解しておくよう、派遣スタッフに教育しています。従い、就業規則に伴う諸規則、特に時間外協定(通称36協定)についても派遣元のものに準じることになります。
その他、主には就業場所での安全衛生面については派遣先にも責務が生じ、派遣先での基準を優先される場合があります。
- Q契約内容(業務内容・就業場所・就業時間など)を途中で変更することは可能ですか?
- A
まずはサンスタッフへご相談下さい。
解説:
原則として、派遣契約で定めた業務内容の変更は認められません。やむを得ない理由で、契約内容を変更する必要が生じた際には、派遣元と派遣先の間で相談し、派遣スタッフ合意の上、契約内容を変更することが可能です。
「派遣先は、派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じること」が規定されています。
- Q派遣スタッフの受け入れについては、どんなことが必要になりますか?
- A
以下内容にてご理解いただけると幸いです。
解説:
受け入れに関する社内アナウンス周知
- 派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明と展開
- 契約期間、勤務する曜日や時間の展開
- 入館証やIDカードの発行
- 社内ネットワーク等の利用手続き
- デスクや事務用品、パソコン機器等の準備
- 業務上必要なアプリケーションのセットアップ
- 業務マニュアルや引継ぎ書の準備
また就業開始初日には、下記のような案内・説明をしていただくと、派遣スタッフは安心して就業することができます。
初日にご案内いただきたい事項の例
- 派遣先責任者および指揮命令者への展開と紹介
- 社内設備・フロア・食堂や休憩室の案内
- コピー機やFAXの場所、使い方
- 備品の保管場所
- 入退室に関するルール(IDや入館カードの使い方)
- オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
- 個人情報・機密情報の取扱いルール
- 業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
- 会社独自のシステムの概要と使用方法
- 座席表・組織図などの配布
- Q派遣で対応できない職種はありますか?
- A
あります。
解説:
労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。 - 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
- Q会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?
- A
出来ません。
解説:
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
- Q派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?
- A
一定の範囲内で可能です。
解説:
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
- Q派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか?
- A
主には以下の4つです。
解説:
1.仕事の指示、業務に関する情報共有
- 業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で対応できますように、お願いします。万が一、契約内容に修正が必要な場合は営業担当にご相談ください。
- 業務上の間違いや、認識・理解の誤りなどが見受けられた場合は、派遣先社員の方と同じようにご指摘いただき、ご指導願います。それでも改善が見られない場合、まずは営業担当にご相談ください。
- 派遣スタッフにも対応業務の前工程や後工程の話など、業務に関連する情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります
2.教育訓練、能力開発
社内の社員の皆様含めた労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、当社からの求めに応じて、当該訓練を実施するよう配慮していただきます。ただし、既に必要な能力を有している場合や当社で同様の訓練実施が可能である場合を除きます。
3.社内コミュニケーション
- それぞれ個人名で呼び、定期的に派遣スタッフと話す面談を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからもご相談がしやすく、安定就業につながります
- 業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となりますので、不参加の際にも不自由を感じさせないようなご配慮をお願います。
4.就業する環境へのご配慮
- 派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、派遣先もその責を担います。派遣先社員に対する対処と同様にご対応ください。また、同種の相談窓口が派遣先社内に存在する場合は、その旨を派遣スタッフへもご案内ください。
- 派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用責任が派遣先企業にあります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
- 派遣先の労働者が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣スタッフに対しても利用の機会を与えていただくよう配慮する必要があります。
- Q個人情報や機密情報の取扱いについてどのような取組みを行っていますか?
- Aサンスタッフでは、2005年にプライバシーマークを取得し、個人情報保護に積極的に取り組んでいます。委託先においても、「委託業務従事者への情報保護教育」「委託先への監査」等を実施し、お預かりした個人情報や機密情報の適切な取扱いに力を入れています。
- Q派遣社員の労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか?
- A
手続きは派遣元ですが、関連書類については派遣先にご協力いただきます。
解説:
労災保険は、あくまで雇用関係のある派遣元で加入していますので、労災保険の給付請求についても派遣元を通じて行います。
当社はその安全基準を豊田自動織機グループの一社として安全ビジョンを掲げており、以下3点をお願いしております。- 発生時にはサンスタッフ営業担当まで必ずご連絡ください。
- 病院での診察が必要な場合は、指揮命令者並びに関係者の方が付き添い願います。
難しい場合はサンスタッフまでご連絡をいただければ営業担当が同行いたします。 - 場合により処置災害であっても、その経緯や原因を調査させていただく場合がございます。 また、派遣社員が労働災害等により死亡または休業したときは、派遣先および派遣元の会社がそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出しなければなりません
- Q当社の都合で、派遣契約を途中で解約することは可能ですか?
- A
原則として、契約の中途解約はできません。
解説:
派遣法においては、「労働者派遣の役務の提供を受けるものは、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として労働者派遣契約を解除してはならない」と規定されています。
ただし、やむを得ず中途解約を行おうとする場合には、派遣先は以下の措置を講ずることが2012年10月の派遣法改正により義務化されました(派遣法第29条の2)。- 派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申し入れを行うこと。
- 派遣先の関連・グループ会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
- 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができない場合には、少なくとも中途解除により派遣元に生じた損害の賠償を行うこと。
- 派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。
- 派遣元から請求があった際は、中途解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすること。
派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ対処させていただいております。詳細は担当営業までご連絡ください。